議事録作成の工数を7〜8割削減!ACES Meetで属人化を防ぎ、誰でも情報を扱える環境に
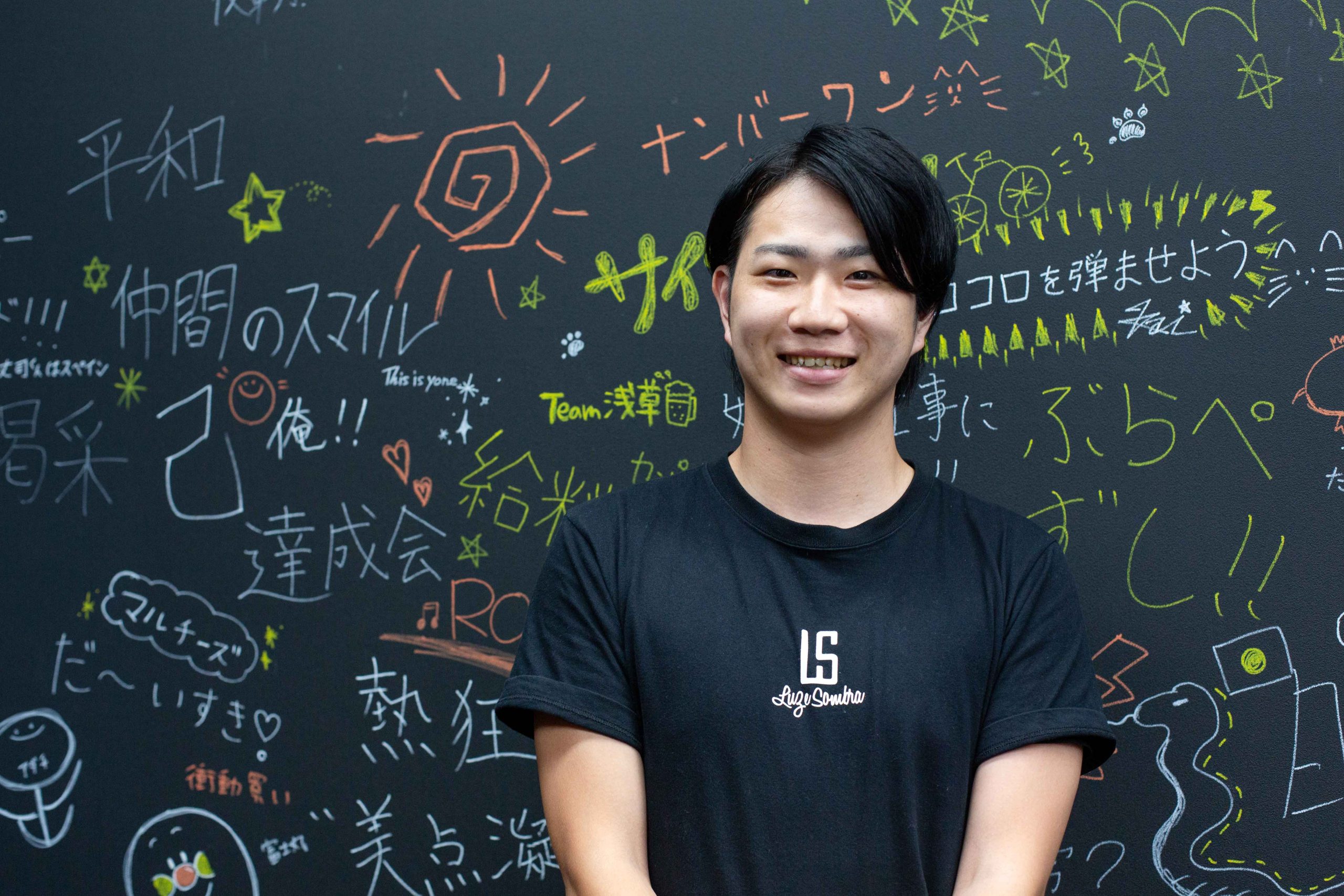
株式会社Stech&Co.
代表取締役
森川 剛 さん
- SES事業
- 人事
- 従業員数:10-50名
導入前の課題
- 面談や商談内容の記録管理が煩雑化し、必要な情報を後から思い出せない場面が頻発していた
- 候補者への同一質問の繰り返しや商談の主導権の不明確さにより、意思決定や信頼構築に支障があった
ACES Meetの活用法
- 面接や商談において、事前に設定したプロンプトをもとにAIが自動で文字起こし・要約を実施
- 要約データのリンク共有やキーワード検索機能により、社内外との情報伝達とアクセス性が向上
導入後の効果
- 情報整理が体系化され、面談や商談内容をすぐに振り返れる体制が整い、情報の資産化が進んだ
- 面接や商談の引き継ぎ精度が向上し、やりとりの重複や判断の遅延が解消された
「エンジニアが正当に評価され、前向きに働ける環境をつくる」
そのような理念を掲げ、2024年に設立された株式会社Stech&Co.は、SES(System Engineering Service)事業を中心に、13名規模の少数精鋭で事業を展開しています。同社では、代表自らが営業・採用・経理などを兼任しており、面接や商談内容の記録・整理が業務の大きな負担になっていました。
この課題を解決すべく、議事録作成の自動化と情報の資産化を目的に、AI議事録ツール「ACES Meet」を導入。要約や共有機能を活用することで、業務効率の向上と情報共有のスムーズ化を実現しています。
本記事では、代表取締役・森川剛氏に、ACES Meet導入の背景や活用法、導入したことによって得られた具体的な成果について詳しく伺いました。
目次
少数精鋭ゆえの業務過多。代表が直面していた情報整理の課題
ーー 御社の事業内容とその特徴についてお聞かせください。
森川様:株式会社Stech&Co.は、2024年9月に設立した会社で、SES事業を主軸とする企業です。従業員数は入社予定者を含め13名ほどで、私を除く全員がエンジニアとして在籍しております。
当社では「エンジニアファースト」を掲げ、高い還元率の実現、単価の開示、案件の選択制度、そし将来的なキャリア形成を支援する「キャリア踏み台制度」といった、独自の取り組みを進めています。キャリア踏み台制度は、転職を前提としたキャリアパスを尊重し、目指す方向性に必要なスキルが身につく案件にアサインすることで、次のステップを後押しする仕組みです。
ーー ACES Meet導入前に、どのような課題を感じていらっしゃいましたか?
森川様:バックオフィス業務全般を私一人で担っており、採用や営業、経理などを並行して進める中で、徐々に業務が煩雑化していきました。事務作業自体に苦手意識はありませんが、面談や商談が連続することで、どの情報をどこに残したかが不明瞭になり、後から思い出せない場面が多く発生していたのです。
面談や商談の内容は録画ツールで記録するという対策はしていたものの、再確認する機会は少なく、結果的にデータを有効活用できていない状況が続いていました。情報の資産化が必要であることは認識していたものの、容易に振り返ることのできる体制が整っていなかったのが実情でした。
ーー 情報が適切に管理・共有されていないことで、具体的にどのような影響が生じていたのでしょうか。
森川様:たとえば、2回目の面接で同じ質問を繰り返してしまうことがあり、候補者に対して不信感を与える恐れがありました。
また、商談の対応においても、やり取りの主導権が自社側にあるのか、相手側にあるのかが曖昧なままとなり、その結果作業が遅れて意思決定が遅れる要因となってしまうこともあったのです。さらにSESという業態の特性上、商談相手が要員を提供する企業なのか、それとも案件を紹介する企業なのかを把握できないまま話が進んでしまい、認識の齟齬が生じる場面も見受けられました。
過去には、業務委託の方にデータ入力を依頼したこともありましたが、入力精度のばらつきや、細かな確認に要するコミュニケーション工数を考慮すると、コストに見合う効果は得られなかったなというのが正直なところです。
要約精度の高さが導入の決め手に
ーー ACES Meetを知ったきっかけと、導入に至った理由をお聞かせください。
森川様:ACES Meetは知人からの紹介で知りました。無料トライアルが可能だと伺い、まずは試してみようと軽い気持ちで利用を開始しましたが、実際に使用してみると、業務効率化につながる可能性を感じました。
導入を決定した最大の理由は、録画データから文字起こし、さらにAIによる要約までを一貫して自動で処理できる点です。これまで手作業で対応していた一連の工程が大幅に簡略化され、ACES Meet導入による業務改善効果を明確に実感できたため、本格的な導入を決断しました。
ーー トライアル利用時に、特に評価されたポイントをお教えください。
森川様:要約の精度が非常に高く、設定したプロンプトに基づいて必要な情報が的確に抽出・整理されている点は印象的でした。人手による要約と比較しても、品質のばらつきがなく、一定水準以上の成果が安定して得られることは大きな利点です。
また、要約スタイルをある程度カスタマイズできるため、自身の業務スタイルに合わせた出力が可能であることも便利だと感じました。面接の録画データを初めてACES Meetにアップロードし、生成された要約を確認した際に、これまで煩雑だった業務が一気に効率化される手応えを感じました。
ーー ACES Meetは、現在どのような業務で活用されていますか?
森川様:主に、面接における記録や振り返り、情報共有のために活用しています。
面接においては、候補者のスキルセットや転職理由、希望条件といった情報を抽出するために独自のプロンプトを設定し、自動要約を行っています。
また、2回目の面接には、私ではなくエンジニアメンバーが担当する場合もありますが、その際に1回目の面接内容が要約された記録として残っていることで、情報共有が非常にスムーズになりました。
ACES Meet導入前は、1回目の面接内容を失念してしまうこともあり、共有が不十分なまま面接を進めてしまうケースがありました。その結果として、先ほどもお伝えしたように既に確認済みの事項を再度質問してしまうなど、候補者とのやり取りに支障が生じる場面も見受けられました。現在は、ACES Meetによる要約を活用することで、こうした情報の行き違いが解消され、面接プロセス全体の精度と効率が向上しています。
情報伝達の手間が激減し、情報資産化の第一歩に
ーー 特に効果的だと感じている活用方法や、導入後に価値を実感された機能があればお教えてください。
森川様:もっとも効果を感じているのは、プロンプトを活用した「必要情報のピンポイント抽出」です。次回以降の面接や商談のために、事前に確認したい観点をプロンプトとして設定しておくことで、文字起こしと要約内容が的確に整理され、手作業と比較しても安定的かつ高い情報整理が可能になりました。
また、導入当初は重視していなかったものの、現在では「共有機能」も重宝しています。ACES Meet上で生成された動画や文字起こし、要約のリンクを関係者に共有するだけで完了するため、情報伝達にかかる手間が大幅に削減されました。さらに、キーワード指定による情報抽出機能も活用しており、必要な情報へ迅速にアクセスできる点には非常に満足しています。
ーー 導入による定量的な効果について、可能な範囲で教えてください。
森川様:正確な数値での計測は行っていませんが、議事録作成にかかっていたコミュニケーションコストが、感覚的に7〜8割は削減されたと感じています。議事録作成を業務委託に依頼していた際は、内容の修正依頼や確認作業に2〜3往復のやり取りが必要になることもあり、次第に依頼自体が負担となっていきました。結果として、自分がやり直すケースも多く、非効率な運用が続いていました。
また、面接や商談内容の振り返り速度も大きく向上しました。これまでは、録画の確認から記録整理までにおよそ1営業日を要していましたが、現在ではほぼ即時で対応できるようになり、実質的には約8時間のリードタイム短縮に繋がっています。
小規模組織にこそ最適なツール。属人化の防止と業務継続性の確保に寄与
ーー ACESのオンボーディングやサポート体制について、どのように感じられましたか。
森川様:サポート担当の方は営業的な押しつけが一切なく、適切な距離感で対応してくださった点が非常に印象的でした。連絡頻度も過不足なく、導入初期の立ち上げもスムーズに進行しました。
サポートを受けて特に有益だったのは、面接内容からエンジニアのスキルを抽出するためのプロンプト設計を支援していただいた点です。私自身が作成したプロンプトと比較しても、ACES側から提供された内容はより精緻に設計されており、必要な情報が的確に抽出されていると感じました。
実用レベルのプロンプトを提供していただき、そのまま活用できたことで、ACES Meetの本格運用へと迅速につなげることができました。
ーー 御社が考える理想的なオペレーション体制についてお聞かせください。
森川様:当社が目指しているのは、「属人化しない運用体制」の構築です。特に小規模なベンチャー企業では、人材の入れ替わりも発生しやすく、情報の引き継ぎが滞ることで業務継続に支障をきたすリスクがあります。
その点、ACES Meetは誰が使っても一定水準のアウトプットが得られるため、情報整理やナレッジ蓄積が特定の人物に依存しずらい点が非常に有効です。情報がツール上に資産として残ることで、担当者が交代した場合でも、スムーズな業務引き継ぎが可能になります。
ーー ACES Meetは、どのような企業にとって導入効果が高いとお考えですか?
森川様:意外と思われるかもしれませんが、ACES Meetは立ち上げ間もない小規模な企業にこそ導入をおすすめしたいツールです。組織の成長初期においては、システム導入に慎重になりがちなフェーズではありますが、実際に運用をしてみると、人件費や工数の削減効果を含め、コスト以上の価値を実感できます。
たとえば、バックオフィス業務を少人数で対応している、あるいは経営者自身が複数業務を兼任しているようなケースでは、議事録作成や情報整理といったノンコア業務が大きな負担になります。ACES Meetを導入することで、これらの作業を自動化・効率化でき、業務時間の短縮と負荷軽減に直結します。
また、小規模な組織ほどナレッジ共有が属人的になりやすい傾向になりますが、ACES Meetによって生成された要約データが情報資産として蓄積されることで、誰でも容易にアクセス・共有が可能になります。人手が限られるがゆえに情報管理に課題を抱えがちな企業にとって、ACES Meetの導入効果は非常に大きいと考えています。特に、面接や商談内容の整理・共有に課題を感じている企業ほど、高い効果を実感できるのではないでしょうか。
- ■お話を伺った方
森川 剛 さん - 株式会社Stech&Co. 代表取締役 新卒採用支援を行うStella Pointにて、理念「半径5m以内の人を幸せにする」のもと、人材紹介や研修などを手がける。エンジニア業界の構造的課題に向き合うため、同社初のグループ企業Stech&Co.を設立。SES業界に根付く不透明な慣習を打破し、エンジニアが正しく評価され、前向きに働ける環境づくりを目指している。
- ■取材・執筆
西條真史


